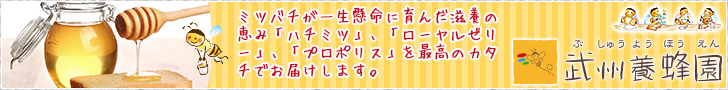文房具朝食会@名古屋で知り合った建築士の富田さんが開催した「日本茶を楽しむ会」に参加してきました。最近、物覚えが悪いので略して「トミティーの茶会」と勝手に呼んでいます。
勘のいい方はわかると思いますが富田さんのお名前とお茶(ティー)を合わせた造語です。
コーヒーを知る上で他の飲料の世界も学んでみようシリーズです。いつからシリーズになったか?なので今日からシリーズにします。前回の紅茶の記事はこちらです。
場所は名古屋の国際センター駅近くの「NO DETAIL IS SMALL」さんです。スペシャルティコーヒーが飲め、オリジナルノートを作れる素適なお店です。
今回は常滑焼の若手作家・渡辺 敏史氏の急須展も開催されているということで渡辺氏の急須でお茶を淹れてくださりました。
この急須の「丸み」がなんともセクシーな感じがします。
富田 崇氏
富田さんにお会いするのは今回で確か3回目です。同級生というのと、学生時代私と同じ卓球部に所属していたということで勝手に親近感を持っています。卓球をかじったことがある方ならわかると思いますが、今の時代(当時も少なかったですが)絶滅危惧種となっているペンの表ソフトラバーの前陣速攻型だったというところも一緒と聞き驚きました。
建築士であり学校の先生もしている富田さんが、なんで日本茶なのか?
きっかけは、学校の生徒さんから中国茶をいただいたことだそうです。せっかく頂いたものなので、美味しく淹れたいけどどうやっていれるのだろうというところから興味を持ちお茶の世界に引き込まれたそうです。
建築事務所のお客様にも、丁寧に日本茶を淹れお客様の声をしっかりヒアリングされているそうです。美味しい日本茶を飲んで心が落ち着きお客様も、自分がどんなものを望んでいるのかをしっかり富田さんに伝えることが出来そうですね。
富田さんのように、色んな顔を持つ人、素適ですね!
トミティーの茶会
もう何杯お茶を飲んだのか?です。
この日飲んだお茶のラインナップはこちらです。
- 煎茶
- 玉露
- 乳山緑茶(抽出法を変えて2杯)
- 白茶(抽出法を変えて2杯)
- 青茶(鉄観音)
- ダージリン
- アッサム
ラインナップとしては以上です。
テーブルの上にこんなのが置いてありました。
これはフレンチのお店でソースを数種類楽しみながら食べる料理に使うお皿だそうです。
お茶の煎りの深さを横軸に。適した抽出温度を縦軸にして茶葉を並べてあります。視覚にパッと飛び込みわかりやすいです。私には真似の出来ない細やかな心配りです!トミティーの人柄があらわれていますね。
淹れて頂いたお茶を私は次から次に飲み干してしまいました。他の参加者の方が全て淹れ終わるまで残しておいて撮影された写真です。
キレイですよね~。
個人的な感想を簡単に。
じっくり腰を据えて美味しい和菓子とともに愉しむなら「玉露」。
がぶがぶと飲むなら「煎茶」。今回飲んだ煎茶は、とにかく甘味とまろやかな「丸味」が逸品でした。
そして液体の色の美しさ(ドンペリのピンクのような)と、さわやかな飲み口の白茶は女性が好むかなと思いました。
今回、ダージリンはファーストフラッシュということでこちらも爽やかな印象を受けました。
真剣な表情のトミティーです。
なぜかわからないですがサルの懐紙(笑)
そして最後に今年の夏大ヒット間違い無し!?の「チャッティー」の紹介です。
朝、出かける時にペットボトルに茶葉と水を入れてチャッティーをセット。これでお昼前には美味しいお茶を楽しめるという画期的なものです。簡単なので、面倒くさがりな私でも使えそうです。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1658b447.9474a58a.1658b448.02768f4b/?me_id=1242374&item_id=10000136&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fecobank%2Fcabinet%2Fchattea%2Fimgrc0070323033.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fecobank%2Fcabinet%2Fchattea%2Fimgrc0070323033.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
【送料無料】ペットボトル用ティーストレーナー(茶漉し)「チャッティー5本セット」当店人気商品!!
|
コーヒーとお茶の共通点と違い
今まで「お茶」について勉強したこと全くありません。今回、参加せさて頂いて私が感じたことをまとめておきます。
抽出に関しては、非常に考え方が似ているということ。時間や温度に関する概念というのは同じだなと思いました。
水に関しても「軟水」を使用するというのは同じです。
同じところで採れた茶葉でも、その栽培方法や加工の方法で風味が変わるというのもコーヒーとやはり同じですね。
保管に関してもやはり同じ部分が多いです。高温多湿を避け遮光性があるものに入れる。
ただ保管する「期間」に関してはお茶の方が、かなり時間経過したものでも美味しく飲むことが出来るという違いは感じました。
飲む「器」に関しては陶器なのか磁器なのかというところをコーヒーよりも大切にするんだなと感じました。
そして一番違うと感じたのは「渋み」に関してです。
コーヒーは99%渋みをネガティブに捉えますが、お茶の世界では「渋み」は大切な要素となります。
たまにはこうして違う世界を見てみることで、確認出来ることや発見することがあるので機会があれば色々参加してみたいです。
楽しく、わかりやすく、美味しい講座を開いてくれたトミティーに感謝です。ありがとうございました。
最後まで、読んでいただきありがとうございました。